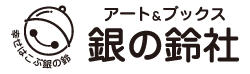西野真由美の社長ブログ◯日本画とポエムが出会う時
西野真由美の社長ブログ◯日本画とポエムが出会う時
6日日曜日、銀の鈴文化サロンで、お話会「日本画とポエムが出会う時」が開催されました。
今春刊行した詩画集『こもりうたのように 美しい日本の12ヶ月』を中心に、著者で詩人の佐藤雅子さんと、佐藤太清美術館顧問の安田晴美さんにお話を伺いました。
じつは、雅子さんは太清画伯の娘さん。そして、晴美さんは、その雅子さんの一人娘。
まず、本書の一月の絵にこめられたエピソードから。
モデルの雅子さんは、赤いおべべに兵児帯しめて、何不自由なく暮らしているお嬢様そのもの。
展覧会の会場で、そうつぶやいたお客様に、雅子さんは、晴れ着の真実を語ったそうです。
絵が描かれたのは、終戦直後で何もない時。
晴れ着は、お母様がご自分の長襦袢を縫い直してあつらえてくださったのです。
そして帯は、画伯の失敗した絹本を、これもお母様が晒して色を抜き、絞り染めにしてあつらえた兵児帯。
人物画はあれを含めて二点しかないといいます。
あの絵から感じる温かな眼差し。
少女の表情や結わかれた髪の先まで、慈しむような視線を感じていた私には、納得のエピソードでした。
誰も入れなかったという画伯の画室に、いつも入り浸りだったという晴美さん。
ここぞという線を描く時の凄まじい気迫。
その一筆を、グッと息を止めてうなりながら描く姿に、画室の傍らで晴美さんもまた息を止めて見入っていたそうです。
画伯のうなり声は、辛さや苦しみなどを一切感じさせない、真に美しい絵を生み出すための呻吟、濾過作業だったのかしら。
うなり声は、産みの苦しみだったのですね。
美術の学校への進学を希望する雅子さんへ、それを許さなかったという画伯。
雅子さんの告白に、ご参加くださっていた画伯のお弟子さんは、たくさんの弟子がいる中で、娘がいたら公平に見られないこと、そして画壇での親の七光りを避けたいとおっしゃっていたと証言され、雅子さんも驚いておられたり。
「児童文芸」2009年10・11月号に掲載されていた、佐藤雅子さんのエッセイ「父の音」。
その単行本のようなお話は、深い愛情がたっぷりのノンフィクション。
画伯と日常生活を共に過ごしてきた娘と孫の目から見た、制作現場の裏話などと一括りにしたくない、貴重なお話を伺うことができました。
西野真由美